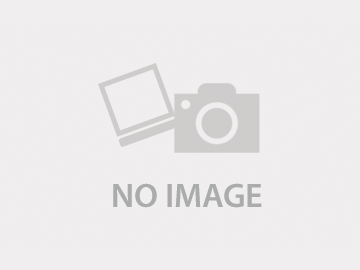先日の投稿でユニバース25の話しに触れましたが、調べてみると、偏った情報になってしまった為、今回は違う視点での記事にしてみました。
最初に答えから伝えますと、
図と身近な例を使って、ユニバース25の流れと注意点を説明します。ポイントは「何が起きたか」「どこに気をつけるか」「人間にそのまま当てはめない」の3つです。
全体の流れ(1枚で見る)
以下は実験で報告された出来事のながれです。矢印にそって読むと全体像が分かります。
[スタート] ねずみ8匹→ えさ・水はある囲い
→ 数がどんどん増える
→ ぎゅうぎゅう(過密)
→ けんかが増える/子育てが乱れる
→ 子どもが生まれにくくなる
→ 全体の数が減る
→ ほとんどいなくなる
何をしていた実験?
・囲いの中で、えさや水を足りるようにしながら、ねずみの数と行動の変化を長い時間観察しました。
・はじめは増えますが、その後はケンカや子育ての乱れが目立ち、子どもが生まれにくくなり、最後は群れが小さくなりました。
よくある説明(ひとことで)
・「過密(人が多すぎる)になると、社会が壊れる」というたとえ話として広まりました。
・研究者本人も「ねずみの話だけど、人間のことも考えている」と書いていて、比喩として有名になりました。
大事な注意(ここが弱点)
下の3つは、実験をそのまま“人間の予言”として信じてよいかを考える上で大切な注意です。
| 視点 | 何が問題になりやすいか | どう気をつける? |
|---|---|---|
| 衛生・掃除 | 掃除や消毒のやり方にバラつきがあり、本当に「理想の環境」だったかははっきりしません。 | 「環境のきれいさ」も行動に影響すると考える。 |
| 出発の数 | たった8匹スタートで、近い血どうしが増える「近交」がおきやすい条件でした。 | 遺伝の影響も混ざっているかも、と考える。 |
| 比べ方 | 比較する対照(他の条件)が足りず、「過密だけのせい」とは言い切れません。 | ほかの原因(衛生・遺伝・配置)もありうると考える。 |
人間にそのまま当てはめない理由
・人間社会は、文化・学校・医療・ルール・家の形など、ねずみの囲いと条件が大きく違います。
・だから「いつでも、どこでも、過密なら必ず崩れる」と決めつけるのは早すぎます。
図で分かる「判断のコツ」
以下の簡単フローチャートにそって考えると、落ち着いて判断できます。
原因は1つ? → いいえ → いくつか混ざっているかも(衛生・遺伝・配置・過密)
↓はい
十分に比べた? → いいえ → 条件の比べ方を見直そう
↓はい
人間にも同じ? → いいえ → そのまま当てはめない・たとえは控えめに
身近な「例え」でイメージ
・体育館の例
体育館に人をたくさん入れて、掃除や換気が少なく、同じ家族だけで固まっていたら、体調や気分が悪くなる人が出てもおかしくありません。ここで起きる問題を「人数だけ」のせいにするのは危険で、「衛生」「距離」「グループの偏り」なども考える必要があります。
・クラス運営の例
えんぴつやノートを前の席にだけ置くと、前の子だけが得をして後ろの子は困ります。人数だけでなく「資源の置き方」も大事、という話です。
これだけ覚えればOK
・観察された流れ(増える→乱れる→減る)は事実として紹介されましたが、原因は1つとは限りません。
・人間への当てはめは「たとえ話」にとどめ、決めつけずに考えましょう。
・役立つヒントは「環境づくり」で、ぎゅうぎゅう詰めや不公平な配置をさけ、休める場と役割のバランスを考えることです。
考えるヒント
こわい物語ほど広まりやすいです。まずは「ほかの原因はない?」「ちゃんと比べた?」と落ち着いてチェックするクセをつけると、ワクチンについても中道で情報に振り回されにくくなります。
ワクチン後遺症患者ですが、時には感情的になりますが、中道な発信をしていきたいと思っています。