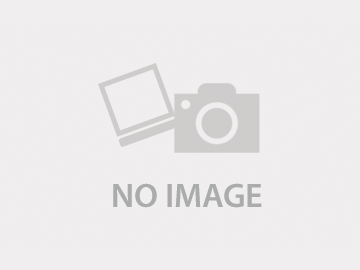いやー、超過死亡に答えられない。新しい厚労大臣もダメでしたね…。
前任の時代から「高齢化が主因」「追加の精査は不要」という姿勢がにじんでいたのに、新大臣の口からも実態把握や検証に踏み込む意思が感じられず、拍子抜けです。
結局、「最初から結論ありき」で議論を閉じるのなら、国民の納得は生まれません。
そして、総理大臣の参政党・神谷氏への答弁で分かったこと。
「おまえもダメだ!」——率直にそう感じました。
的を射た問いに、核心を外す言い回しの連続では、国会答弁が“説明”ではなく“回避”になってしまいます。
人気総理は法案が通りやすい
人気が高いうちは「今なら通る」とばかりに、大きな制度変更が一気に進むのが日本政治の常です。
郵政民営化の時も、熱気と勢いが意思決定を後押ししましたが、熱狂の陰でほころびや副作用が置き去りになりました。
だからこそ今は、雰囲気ではなく中身を見るブレーキ役が必要です。
早速の疑問点
・米の「増産」から「減産」へあっという間の方針転換
・NTT株売却論の再燃。国有資産の切り売りを財政論で片付けてよいのか。
・「ワクチンの懸念はない」で思考停止。懸念が“ない”ことを示すデータ設計こそ求められます。
どれも生活直撃のテーマなのに、説明責任の温度が低すぎます。
政策は「やってみてダメなら戻す」でもよいのですが、戻すならなぜ戻すのかを丁寧に示すべきです。
スパイ防止法は国民不利にしてはならない
スパイ防止法の立て付け次第では、公益通報や取材・市民の調査活動まで萎縮しかねません。
政権が代わっても恣意的に運用されない歯止め、独立した監視機関、厳格な定義、濫用時の救済ルートが不可欠です。
「安全保障」の名の下に、国民の目と口をふさぐ諸刃の剣にしてはならないのです。
総理の看板は変われど
看板は変われど、中身はほぼ同じなら、結局は同じ失敗をトレースするだけです。
米政策は需給で語り、通信は財政で語り、医療は空気で語る——論点ごとに物差しを替えれば、全体最適は生まれません。
政治の役割は、分野ごとの“正論”を束ね、国民にとっての“納得解”へと編み直すことです。
新厚労大臣にはガッカリ
「超過死亡を調べようとしない国」というレッテルは不名誉ですが、現状の対応ではそう受け止められても仕方ありません。
まずは定義・手法・前提の透明化、第三者検証、仮説の併走(感染流行・医療アクセス・慢性疾患悪化・薬剤影響・ワクチン影響など複合要因)を並走させる設計が必要です。
“結論”ではなく“プロセスの信頼”を取り戻してください。
「反ワク」呼ばわりへの違和感
この話題を出すと「反ワクチン」と言われがちですが、ラベリングは議論を貧しくします。
因果の立証は困難でも、統計的シグナルが見えたら「仮説として疑う」ことは公衆衛生の常道です。
ワクチンを疑うのも必然——小泉構文風に言えば、「疑わない理由がないから疑う」のです。
代表質問で見えたもの
神谷氏の問いは、生活者目線のテーマに直球で、答弁側の視線の高さが際立ってしまいました。
減税、移民・外国人政策、安全保障と権利保護、成長と分配——いずれも“言い換え”で通り抜けられる段階ではありません。
「説明」と「再考」の連鎖が始まらない限り、期待は失望に変わるだけです。